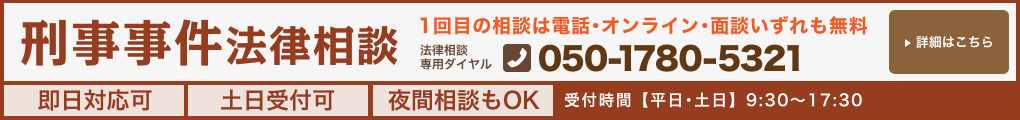刑事事件ブログ
過去の記事を見る
- 4月
- 16日
- Mon
外国人の刑事事件においては、どのような判決を受けるかということ以上に、今後も日本に残れるのかという在留に関する問題が重要視されることがあります。
今後も日本に残れるのかということについて考えるとき、①その事件が退去強制事由に該当するのか、②また在留特別許可が受けられるような事情があるかどうかについて、それぞれ検討する必要があります。
①の退去強制事由につきましては、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者といった在留資格を有する方と、それ以外の在留資格を有する方とで基準が異なります。たとえば、傷害事件を起こした場合、前者の資格を有する方の場合は、たとえ懲役刑となっても執行猶予が付けば退去強制事由に該当しないのに対して、後者の場合は、懲役刑が科されると執行猶予が付いたとしても退去強制事由に該当します。
したがって、後者の場合は、示談による不起訴を目指すなど、懲役刑を科されないことを目標とする弁護活動が必要になります。なお、薬物犯罪など、前者の資格を有していても有罪の判決を受ければただちに退去強制事由に該当する犯罪類型もあります。このように、退去強制事由を把握したうえで弁護活動に臨むことが大切になります。
②の在留特別許可につきましては、あくまで「特別」の許可ということで、明確な基準はありませんが、法務省のホームページにて許可・不許可事例が公表されていることが参考になります。公表されている事例を見る限り、刑罰法規違反があったケースにおいて、在留特別許可を得ることは極めて難しいといわざるを得ませんが、完全に否定されているわけではありません。
刑事事件において身柄拘束されている場合においても、在留資格更新手続きは行う必要があります。更新手続きを行わない場合、刑事事件の処分内容が退去強制事由に該当しないときも、オーバーステイにより退去強制手続が開始することがあります。私も、身柄拘束中の方の代理人として、入国管理局にて在留資格更新手続きを行ったことがありますが、そのときは無事更新が完了しました。
なお、入国管理局にて手続きが行えるのは入国管理局発行の届出済証明書を有する弁護士に限られることに注意が必要です。
外国人の刑事事件においては、上記のとおり、日本人の刑事事件以上に、早期に対処する必要のある問題が生じます。当事務所は、県内9カ所(名古屋丸の内、名古屋新瑞橋、名古屋藤が丘、小牧、津島、春日井、高蔵寺、日進赤池、岡崎)及び岐阜大垣に事務所があり、早期の面談相談を行いやすい体勢を整えております。何かありましたら是非お気軽にご相談頂ければと思います。
高蔵寺事務所 弁護士 服部 文哉
- 4月
- 2日
- Mon
警察官や検察官は、取調べの最後に、被疑者・被告人がその日の取調べで話した内容をまとめた紙を作成することが多いです。この紙のことを、「調書」といいます。
警察官や検察官は、被疑者・被告人に対し、調書の内容を確認した上で、調書の最後に名前を書いて指で印を押す(署名押印)よう求めます。
では、調書に署名押印をすると、どうなるのでしょうか。
署名押印された調書は、裁判上不利な証拠となる可能性があります。客観的な証拠が足りておらず、本来であれば嫌疑不十分として不起訴になる可能性があるケースでも、自白調書に署名押印しまったことで、起訴されてしまうこともあるのです。
そして、いったん調書に署名押印してしまうと、裁判になって、あれは間違いでしたと話しても、認めてもらえない可能性が非常に高いです。それは、署名押印前には必ずその内容を読んで、間違いないかを確認していること、調書に自分が話していない不利な内容が書かれていれば、通常は署名押印前に抗議するはずだと考えられるからです。
被疑者・被告人の権利として、調書に残したくない場合には、署名押印を拒否することができます(署名押印拒否権)。また、調書の内容に間違いがあって、修正してほしい場合には、署名押印前に内容の修正を求めることもできます(増減変更申立権)。それでももし修正してくれない場合には、署名押印自体を拒否することにより対応しましょう。
なお、署名押印を拒否したり、修正を申し立てたことで不利に扱われることはありません。
できる限り早めに、弁護人と今後の防御方針や取調べへの対応方法について話し合うことで、意図せず不利な調書をとられてしまうリスクを回避できる可能性があります。
もし、ご自身や身近な方が嫌疑をかけられた場合には、一度弁護士にご相談下さい。
春日井事務所 弁護士 友近 歩美